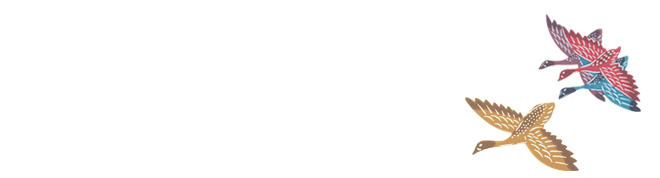
〈 目次 〉
1 自己紹介
(1) 故郷の紹介
(2) 幼少期
(3) 小学生時代
(4) 中学・高校生時代、福岡視力障害センター時代
(5) 本校研修課生時代
2 企業内理療師の役割と今後の課題
1. 企業内理療師(ヘルスキーパー)とは…?
2. 企業内理療師の魅力
3. 企業内理療師数増加の要因と今後の課題
4. 産業保健スタッフとしての役割を果たすことこそが大切
5. 企業内理療師に求められる姿勢
① 誇りと責任感・感謝
② 有資格者だからこそできる施術を目指す
③ 職場の中の理療師だからこそできる施術やコミュニケーションを模索する
④ 常に自分に厳しく評価する
6. この職を守り、発展させて行くために
3 視覚障害者の自立のために
(1) ≪「自ら機会を創り出し、機会によって自らを変えよ」≫
(2) 過去と他人は変えられない。自分と未来は変えられる。変えられることは変える努力をしましょう。変えられないことはそのまま受け入れましょう。おきてしまったことを嘆いているより、これからできることを考えましょう。
(3) 「褒めい謗らいや世ぬ中野習い 沙汰ぬ無ん者ぬ 何役立つか」(ふみいすしらいやゆぬなかぬならい さたぬねんむぬぬ ぬやくだつか)
4 最後に
>>>>>
1 自己紹介
皆さん、こんにちは。
只今、司会の先生からご紹介頂きました、本校研修科卒業生で、現在、福岡市内のIT会社で企業内理療師(所謂ヘルスキーパー)をしています、田里友邦と申します。
2013年から、全国の企業内理療師の団体の幹事を、先月からは本校同窓会の会長もさせて頂いています。
本日は進路講演会にお招き下さいまして、有難うございます。
私自身、まだまだ大変未熟で、周りの方々にご迷惑やご心配をかけたり、多くのご指摘を頂いている身ですので、皆さんのお力になる話ができるか自信はありませんが、ほんの少しでも参考にして頂けましたら幸いです。
(1) 故郷の紹介
まず、簡単に自己紹介いたします。
私は、沖縄県の石垣島という離島の北部にある明石(あかいし)という集落の出身です。
石垣島は、沖縄本島から約440KM離れた離島で、人口約4万5千人ほどの島です。
石垣島と聴けば、皆さんどのようなイメージをお持ちでしょうか。
マスコミ等の影響で、海や空が青く美しく、自然が豊かで、島の人はのんびり生活していて、長閑(のどか)な楽園の様な島というイメージをお持ちの方も多いと思います。
その様なイメージが100%間違えている訳ではありませんが、石垣島がその様に過ごしやすい地域になったのは、私が生まれる前後の頃のことです。
第二次世界大戦の頃、石垣島はマラリアという感染症や米英の空爆等で、多くの尊い人命が奪われました。
戦後、沖縄本島で中北部の住民の土地が、米軍に多く奪われたことも一因で、当時の琉球政府の主働で、人口が大幅に減った石垣島等の県内離島や、ペルー・ブラジル・ハワイ等広大な土地がある海外に、沖縄本島中北部の住民を移住させる≪開拓移民事業≫が行われました。
私の祖父母も、その開拓移民事業に応募し、沖縄本島から石垣島に移住いたしました。
今でこそ、沖縄本島から石垣島迄は、飛行機で僅か1時間弱で行くことができますが、当時は船舶で数日かかり、又、大きな港が整備されていなかったため、港の沖合いで小型船に乗り換えて上陸する必要があったそうです。
私の祖父母が移住した石垣島北部の明石は、砂浜とジャングルの広がる土地だったため、家屋や畑・道路を作る作業を一から行ったそうです。
電気・電話等のインフラが通ったのは、移住してから十数年経過した昭和40年代前半で、それまでは、今では想像もできない様な苦労をして来たそうです。
私の生まれた集落は、その様に、戦後、沖縄本島から移住して来た人が過酷な状況の中、協力しあって開拓して来た集落ですので、沖縄県内でも、他の地域に比べ、助け合いの精神と開拓心が高いと言われています。
私が生まれた頃には、既に電気も電話も水道も通っていて、それほど僻地と感じることはありませんでしたので、私たち移民第三世は殆ど苦労を経験せずに育ちましたが、移民第一世に当たる祖父母の世代の方々から、移民して来た頃の苦労話を身近に聴いて育ちましたので、集落で育った者は≪助け合いの精神≫と≪開拓の精神≫をとても大切にしています。
ここまでは、私の故郷・石垣島の明石集落の歴史と、その影響で育んだ姿勢についてお話いたしました。
(2) 幼少期
その石垣島では、小学校1年生の1学期迄過ごしました。
自宅から徒歩5・6分の所に海がありましたので、夏になれば毎日夕方、母や同級生の家族と共に、海に行って遊んでいました。
自宅の庭や学校で木登りをしたりもしました。
私は今は全盲ですが、小学6年生迄は左目の視力が0.03ほどありましたので、自転車に乗ったりもしました。
ただ、0.03という視力はけっしてそれほど見えている訳ではありませんが、生まれた時からその視力の私にとっては、十分に見えているつもりでしたので、皆と同じ様に自転車に乗ろうとし、芋畑に突っ込んでしまうこともしばしばで、周りに心配をかけていました。
それでも、自転車に乗ることを止めませんでしたので、今思えば、私は幼い頃から我(が)が強い性格だったのかもしれません。
(3) 小学生時代
小学1年の夏休みに沖縄本島に引越し、1年生の2学期・3学期を普通学校に通い、2年生から沖縄盲学校に転校いたしました。
おそらく地方の盲学校は概ねどこも同じだと思いますが、生徒の数が少なく、先生方の数が生徒とほぼ同じぐらいいらっしゃいましたし、また当時の沖縄盲学校の理療科の先輩方が、行事や休み時間等の際、とても私を可愛がってくれたこともあり、大人と接する機会が、普通学校に通っている生徒に比べ、とても多かったと思います。
先ほど私は幼い頃から我が強い性格だったとお話しましたが、それに加え、理屈っぽい性格でもありましたので、先生や先輩から何かを教えて頂いたり、ご注意頂いても、そのまま素直に「はい」と答えることは少なく、「どうして?」「理由は?」「何のために?」「他に方法はないの?」等と質問ばかりし、「ああいえばこういう」と苦笑されることが多かったと記憶しています。
学校の行事で行った公園に、休みの日に朝から一人で遊びに行って、帰りに迷子になって夕方まで歩き回って、親や先生に心配をさせてしまうなど、大変ヤンチャな性格でした。
ただ、今考えればとても有難いなぁと思うのは、そんな風に迷子になって心配をかけることがあっても、親や先生方は、けっして、「何かあったらいけないから、一人で外出するな」と叱った大人は一人もいなく、「心配するから、出かける時はちゃんと言って行きなさい」「迷子になったら電話をしなさい」等と注意をしてくれたことです。
もし、親や先生方が、万が一のことだけを考え、一人で何もさせてくれていなければ、今の私はなかったと思います。
そういった意味では、私は本当に本当に恵まれた環境で幼少期を過ごすことができたと感謝しています。
父親がギャンブル依存症で祖父母の財産を食いつくし、家庭にお金を入れなかったこともあり、小学5年生の時に両親が離婚いたしましたが、子供の頃から良く母に言われていたことは、
「親の方が先に死ぬんだから、親を当てにしないで、ちゃんと自立しなさい」
「見える人でも自分一人の力で生きて行ける人はいないんだから、見えなければ尚更難しい。困った時には素直に人の協力を受け、その代わり、自分もちゃんと相手の役に立てる人間に成りなさい。意地を張って人の協力を拒めば損をするし、自分が人の世話になるだけでもいけない」
ということを常々言い聞かされて来ました。
(4) 中学・高校生時代、福岡視力障害センター時代
話は変わりますが、皆さんは沖縄の≪三線≫という楽器をご存知でしょうか。
三線についての詳しい説明は今回は割愛いたしますが、私はその沖縄の歌三線を、小学5年生の頃から教わり始めました。
始めは、盲学校の職員で、歌三線の教師免許もお持ちの先生から教わり始め、中学生の頃から、地域の教室に通い始めました。
学べば学ぶほど、もっともっと専門的に勉強したいという思いが増して行きました。
音楽の事業の中で少し体験させたり、部活動として歌三線を教えている学校は沖縄には数多くありますが、正式な科目として、専門的に教えている学校は沖縄でも≪沖縄県立南風原高等学校≫と≪沖縄県立芸術大学≫しかなく、その南風原高校がたまたま、沖縄盲学校から徒歩10分ほどの近隣にありましたので、中学生の頃は、南風原高校への入学を検討いたしました。
私の一つ先輩が普通高校への受験を希望し、その先輩のおかげもあり、その年から普通高校の点字での受験が認められました。
そういった背景もあり、南風原高校の受験を検討しましたが、最初にも話しました通り、私は大人と接することが多く、同世代の人との関わりがあまり得意ではありませんでしたので、両校の話し合いの結果、≪校種間交流≫という制度を使い、南風原高校の三線の授業である『郷土の音楽』という科目を、盲学校の高等部に在籍しながら受講させて頂くことになりました。
≪校種間交流≫とは、自校にない教科を他校で受講した際、自校の教科を受講したものと見なし、単位が得られる制度です。
中学・高校生の頃は、この様に、地域の教室や南風原高校の授業で沖縄の歌三線をみっちりと学びました。
県立芸術大学に入学し、更に深く沖縄の伝統音楽を学びたいという気持ちも強くありましたが、やはり同世代の人とラポールを形成する自信が中々持てませんでしたので、沖縄盲学校の高等部卒業後は、まずはいったん慣れ親しんだ沖縄盲学校ではなく、全く環境を変えて、福岡の視力障害センターの理療科に入ることにいたしました。
手に職を持っていた方が無難ですし、国家試験に向けて勉強するのには、若い方が優位だろうし、芸術大学に入学するのは、福岡で人間関係の修行を積んでからでも遅くはない…と考え、福岡視力障害センターの理療科に入りました。
ですので、理療科に入ったばかりの頃の私は、大変お恥ずかしいのですが、「知識と技術を身に付け、患者さんを楽にしたい」という純粋な思いをあまり強くは持っておらず、「沖縄の音楽だけでは生活できないので、とりあえず理療の免許を取っておこう」という程度の気持ちしかありませんでした。
(5) 本校研修課生時代
そんな私を変えて下さったのが、本校の研修課のI先生です。
私がお世話になった本校理療科研修科産業理療コースで担任をして下さったのが、I先生でした。
理療という職がどんなに奥が深く、魅力のある専門職か、もしI先生にお会いしていなければ、私は一生気が付かず、ただ単に「視覚障害者にとって最もハンディーが少ない有望な職だから」という理由だけで続けていたかと思います。
研修課には三つのコースがありますが、産業理療コースを
選んだ理由も、「もし運良く大企業に企業内理療師として就職できたら、楽でいいなぁ」という程度の意識しかありませんでした。
でも、本校に入学してI先生のご指導を受ける様になって、産業衛星分野で理療師が果たすべき役割の責任の大きさと魅力を知ることができました。
理療師として最低限必要な知識や技能を厳しく、でも丁寧にご指導頂けたことを、本当に感謝していますし、知識や技術だけにとどまらず、持つべき姿勢を、言葉だけではなくご自身の生き様で示して下さったI先生と出会えたことを、とても幸せに感じています。
2 企業内理療師の役割と今後の課題
先生方の熱心なご指導と積極的な職場開拓のおかげで、2006年3月、私は無事に本校研修課を卒業させて頂くことができ、翌月の4月から、今の職場であるIT会社に就職することができました。
ここまでは、私の生い立ちについてお話して来ましたが、次に、企業内理療師の役割と今後の課題について、私見をお話させて頂きたいと思います。
なお、これから話すことは、企業内理療師当事者の中でも様々な異なる考えをお持ちの方がいることもご理解の上で、一個人の意見としてお聴き下さい。
1. 企業内理療師(ヘルスキーパー)とは…?
今さら確認するまでもありませんが、法人に雇用され、社員(職員)の心身の健康の
維持・増進、疾病の予防や改善のため鍼・灸・手技療法施術を行ったりセルフケア指導を行う鍼師・灸師・按摩マッサージ指圧師国家資格有資格者を一般に「 企業内理療師 」・「 ヘルスキーパー 」とよびます。
勤務先は企業とは限らず、行政機関や公益法人の場合もありますので、私個人的には
「企業内理療師」という呼称に違和感を感じます。
又≪ヘルスキーパー≫という呼び方は典型的な和製英語ですが、直訳すれば≪健康を維持する≫という意味で、健康増進に関わっている産業保健スタッフは理療師以外にも他にも存在することから、理療師に限って健康の維持を意味するヘルスキーパーと呼ぶ事は私には適切とは思えません。
業務内容からみると「産業理療師」と呼ぶのが的を得ていると個人的には感じています。
ただ、私個人がどう感じようとも一般には「企業内理療師」「ヘルスキーパー」という呼称が浸透していますので、其のことについて、この場で意義を唱えるつもりはありません。
2. 企業内理療師の魅力
どういう呼び名であったとしても、私はこの職に誇りを感じています。
他社の企業内理療師の方の中には、職場名のブランド力に因る社会的地位や収入の安定といった点に憧れこの職を選択される方も多数いらっしゃいます。
勿論、人それぞれ色々な考え方や価値観があることが自然かと思いますので、其の様な動機で企業内理療師に就職する方がいらっしゃる事を批判するつもりはありません。
ただ、私がこの職に誇りを感じているのは、その様なメリットがある事も理由の一つですがその様な理由以上に寧ろ、東洋医学を学んだ私たち理療師の知識や技術は努力と工夫次第で産業衛生の分野でもっともっと活かせると思うからです。
職場状況を理解した理療師が施術に当る事で、利用者個々の状況に応じた施術が行えますし、利用者の愚痴や悩みを丁寧に傾聴することができれば、体のみならず、心も楽になっていただくことができます。
特に職場内での愚痴や悩みは、守秘義務の観点から社内の人にしか話せない内容もあり、かといって職場内で一対一でゆっくりお話できる機会はそれほど多くありませんので、企業内理療師が施術を行いながら伺うことができれば、意義があるかと思います。
他の産業保健スタッフと連携を執ることができれば、更に其の質は向上すると思います。
これらのことは、社外の治療院への委託では難しいことで、そこにこそ私たち企業内理療師のレゾンデートルがあるのだと思います。
3. 企業内理療師数増加の要因と今後の課題
しかし現実には、私を含め多くの企業内理療師は其の様な役割を十分に果たしているとはいえないのが現状だと私は感じています。
ここ数年、企業内理療師を採用する企業が増加して来ているといわれていますが、その背景は、私たち企業内理療師が産業衛生分野でしか果たせない役割をしっかり果たしてその役割が理解・期待されて来たからでは残念ながらなく、障害者法定雇用率を達成することを目的に採用が増えているのが実態かと思います。
今後も暫くは、法定雇用率達成目的のために、企業内理療師採用は増加するでしょう。
しかし、大企業の多くは既に法定雇用率を達成しており、このままいつまでも、企業内理療師が増加して行くとは考えられません。
又、障害者法定雇用率は障害の種類ごとに設定されている訳ではありませんので、雇用に当たって設備整備等に経費が懸からない他の障害をお持ちの方の採用が広がれば、自ずと企業内理療師の採用数は減少します。
一方、中小企業では、まだまだ障害者法定雇用率を未達成の所も少なくありませんが、中小の企業で企業内理療師を雇用できる体力のある企業はそれほど多くはないかと思います。
4. 産業保健スタッフとしての役割を果たすことこそが大切
この様に考えて行くと、企業内理療師が職場更に社会から信頼され必要とされるためには 職場の中の理療師だからこそ果たせる役割 を担える様になる必要があると私は思います。
近年の動きとしては、中小企業が鍼灸院から治療家を派遣して貰い、会議室等で従業員を治療して貰うケースも出て来ています。
この様な動きは今はまだ、企業内理療師を雇用する体力のない企業が中心ですが、今後多くの大企業が障害者法定雇用率を達成すれば、わざわざ視覚障害者を企業内理療師として雇用するメリットは小さくなる訳ですので、コスト軽減のために企業内理療師雇用を見直して、鍼灸院からの派遣という形態に変えられる動きが広がる可能性も、十分考えられます。
プロ球団も持つ某大手企業が福利厚生の一環で、マッサージ店と提携し、社内にマッサージ店を開き、市場よりも安価な価格で従業員に施術を提供するという報道が数年前にあり、話題になりました。
この事例に関しましては、報道だけでは、あんまマッサージ指圧師の国家資格を有する者が施術に当るのか施術所の開設届を保健所に提出しているのか等詳細が不明ですが、いずれにいたしましても、類似の動きが出て来るのは時間の問題かと思います。
この様な動きは、理療師の職域開拓や労働者の福祉の増進といった観点からは歓迎すべきことかもしれませんが、産業衛生分野での理療の専門性という観点からは懸念を感じます。
又前述した様に法定雇用率達成だけを目的に企業内理療師制度を導入した企業の中には、利用者を「お客様」ととらえ、誕生日の日にプレゼントをしたり、料金をチケット制にしてまとめ買した人におまけをしたりーーなどという、気になる取り組みを行っている企業もあるようです。
企業内理療師は、 単に企業に雇用される理療師なのでしょうか?
ただ単に沢山の人を施術したら良いのでしょうか?
産業保健スタッフの一因として役割を果たすことこそが、企業内理療師のレゾンデートルを高めて行くのではないでしょうか。
この職を守り発展させるためには、日頃から理療師として研鑽すると共に、産業保健スタッフの一員として、≪職場の中にいる理療師だからこそ果たせる役割≫を模索する必要があるかと私は思います。
5. 企業内理療師に求められる姿勢
それでは、 職場の中の理療師だからこそ果たせる役割を担うためには、 どのような姿勢で臨むことが必要なのでしょうか。
それぞれの社風等にも因るかと思いますが、次の4つは必須かと思います。
① 誇りと責任感・感謝
まず第1は、私たち自身が理療師である事に誇りと責任感を持ち、この職へ付けた事に感謝することだと思います。
私たちは、自分たちの力だけでこの仕事に付けている訳ではありません。
皆さんご承知の通り、戦後直後、占領軍政府指令で「東洋医学は不衛生で科学的根拠がない」と規制されそうになったことがあります。
多くの医療界、理療関係者の諸先輩方のご尽力で其の動きを食い止め、今私たちはこの仕事を行うことができています。
又、 視覚障害者の職を守るために、晴眼者の進出をもっと規制すべき という政治的主張を屡々お聴きしますが、視覚障害者は既に十分社会から配慮を頂いています。
通常、理療教育を受けるためには、数百万~千数百万の授業料が懸かりますが、視覚障害者は所得に応じ、無料であったり、大幅に免除して頂いています。
更には、晴眼者のあんまマッサージ指圧師数を調整することで視覚障害者の職を守るために、あはき法第19条に基づき、あんまマッサージ指圧師養成校の定員が制限されています。
この様に、視覚障害者は既に充分社会から配慮を受けていて、私たちはこの事を当り前と感じてはいけませんし、むしろ感謝し、研鑽を積む姿勢が大切かと思います。
職を守るために晴眼者の進出に反対することは、一時的には効果があるかもしれませんが、長期的にみれば、理療師に対する社会からの信頼を損なってしまうのではないでしょうか。
ハードルが高いあんまマッサージ指圧師にならずに整体師と称して働く晴眼者が多い。
あんまマッサージ指圧師が国家資格であることを知らずに、逆に整体師を国家資格だと誤解している人が多いと言う調査結果がありますが、この調査結果が、其のことを示しているのだと思います。
その様な意味で、まずは私たち自身が理療師であることに感謝し、誇りと責任感を持つことが何より大切ではないかと申しました。
② 有資格者だからこそできる施術を目指す
2つ目は、私たち理療師が≪有資格者だからこそできる施術≫を行える様になることです。
国家資格を有しない整体師等の施術者を違法だと批判することに精一杯取り組まれている方々がいらっしゃいます。
確かに、国家資格を持たない者があん摩・マッサージ・指圧、鍼、灸の施術を業とすることはあはき法第1条違反ですが、それでは私たち有資格者がどれだけ≪有資格者だからこそできる施術≫を行えているでしょうか。
お恥ずかしい話しですが、私は未だその様な施術をできている自信はありません。
無資格者を批判することは法的には正当な権利かもしれませんが、私たち有資格者が≪有資格者だからこそできる施術≫を行えて初めて、説得力があるのではないでしょうか。
その様な施術ができていない状態で単に違法だと批判することは甘えでしかなく、その様な政治的活動は、逆に世間から信頼を失うことに繋がるかと思います。
あんまマッサージ指圧師を国家資格だと知らずに、逆に整体師を国家資格だと勘違いしている人が多いのは、その様な一因もあるのではないでしょうか。
もし私たち有資格者が≪有資格者だからこそできる施術≫を行えているのであれば、整体師等の無資格者が増えようが減ろうが、社会から必要とされるかと思います。
どんなに安価で便利な即席麺やレトルトカレーが普及しても、本場の昔ながらのラーメン店やカレー屋さんは来えません。
それと同じかと思います。
又、私が幹事をさせてもらっているヘルスキーパー協会のメーリングリストで、理療師が行う施術は≪治療≫が目的なのか、≪癒し≫
が目的なのかという議論が行われたことがあります。
≪治療≫という用語を、≪医療機関で医師が行うもの≫、もしくは、≪医師の指示に基づきコメディカルスタッフが医療機関で行うもの≫と捉えれば、企業内理療師の施術は 治療には当らないかもしれません。
しかし、 治療 という言葉を使うか否かに関わらず、有資格者である以上、 受診者の症状を防ぐ、軽減することを目指すことが責任ではないでしょうか。
単に癒しを目的にした施術を行うのが目的であれば、理療師が企業内に存在する必要があるのか、私は疑問です。
理療師が治療を行えば、もし事故等あった時に責任を取るのは企業だから、理療師が治療を行うことを望まない企業が多いというご意見もお聞きしますが、癒しを目的にした施術なら責任を取れ、治療なら責任を取れないという理屈に、法的根拠があるのか疑問です。
治療にせよ、癒しを目的にした施術にせよ、万が一事故等あれば責任が生じます。
治療を行うにせよ癒しのための施術を行うにせよ、その様な事故を防ぐために、全監注意義務をはらい、問診や触診等を丁寧に行い、相手の症状に応じて自分の能力の範囲で施術する、自分の能力で対応できない場合には、適切にリファーする==ことが責任ではないでしょうか。
施術という言葉を使うにしても、治療という言葉を使うにしても、利用者から「気持ちが良かった」と喜ばれただけで満足してはならず、症状を防ぐ、軽減することを目指すのが有資格者の責任かと私は考えています。
この様な意味で、≪有資格者だからこそできる施術≫を行える様になることが何よりも大切かと申しました。
③ 職場の中の理療師だからこそできる施術やコミュニケーションを模索する
3つ目は、職場の中の理療師だからこそできる施術やコミュニケーションを模索する事 です。
先にも述べました通り、今後多くの企業で障害者法定雇用率が達成されれば、自ずと社外の鍼灸治療院やマッサージ店への委託等に置きかえられる可能性は十分考えられます。
だからこそ、私たち企業内理療師は、≪職場の中の理療師だからこそできる施術やコミュニケーション≫を模索していかなければ、この職を守り発展させることは難しいかと思います。
どのような施術やコミュニケーションが職場の中の理療師にこそできるものかは、簡単に答えが見つかるものではないかと思いますが、まずは、私たち企業内理療師が、それぞれの職場の状況や、産業衛星全般のことをもっと知る必要があるのではないかと感じます。
④ 常に自分に厳しく評価する
4つ目は、社会人としても理療師としても、常に≪「厳しく自分を評価すること≫かと思います。
性別や年齢・学歴・傷害の有無等に関わらず、人は誰でも自分一人の力で生きて行ける人はおらず、必要な時に他人の支援を受けることは決して恥ずかしいことではありません。
私たち視覚障害者の場合は、他人の支援を必要とする場面は、晴眼者に比べて一層多いのが一般的かと思います。
ITの発展に伴う情報格差の縮小やハード面でのバリアフリーの浸透等のお影で、昔より人の援助を受ける必要のある機械は減ったものの、それでも自力でできる事には限界があり、晴眼者に比べ援助を頂く機会は多いかと思います。
多くの方々のご支援を頂けている事に感謝することはとても大切ですが、人に甘える事に慣れ過ぎていないか、できる事までお願いしていないか、常に厳しく自分と向き合う姿勢が必要かと思います。
できることまで甘えて人に行ってもらっては、「障害者と関わるのは大変」という印象を与えかねません。
ハンディを補うために一定の支援を受ける事は決して恥ずかしいことではありませんが、努力や工夫を行い、できることは自分で行う姿勢も大切かと思います。
少なくても企業の中で働く以上は、メールの送受信やインターネットの閲覧、エクセルやワードを使った簡単な資料作成等のPCスキル、身近な場所に関しては単独歩行ができる能力等は備える必要があるかと思います。
又、企業内理療師のもとに受診にお見えになる方は、同じ職場内の従業員です。
職場に雇用された理療師が安価で施術するということは利用者から見た場合、思う様な効果が出なかった場合でも、正直に言いにくいことが考えられます。
私たちはこのことを強く意識し、施術効果に関しても、利用者から喜ばれた時ほど其の言葉をうのみにせず、本当に適切な施術ができているか、常に厳しく向き合う必要があるかと思います。
ここまでは、 職場の中の理療師だからこそ果たせる役割を担える様になるために私が必要かと考える姿勢を4つお話しさせて頂きました。
企業内理療師が従業員に施術を行う事に因る生産性や医療費減少等の効果については、鍼治療に関しては、福岡大学の医師・向野先生等の研究発表がありますが、あんまマッサージ指圧施術による医療費軽減や生産性向上への効果は、残念ながら未だ医療経済学上では必ずしも充分に証明されていません。
しかし、科学的な照明が現段階でされていないにしても、私たちが施術能力を高めることによって、その様な効果を利用者に感じて貰うことは十分可能かと思います。
6. この職を守り、発展させて行くために
企業内理療師という職域を守り発展させるために今後何が必要か、私なりの考えをお話しさせて頂きました。
皆さん、企業内理療師という職を、少しでもイメージして頂けましたでしょうか。
私は、企業内理療師(ヘルスキーパー)という呼称は好きではありませんが、どういう故障であっても、私はこの職に魅力を感じ、誇りを持っています。
今はまだ理想の企業内理療師像には程遠いですが、工夫と努力を続けてフェスティーナレンテに近づいて行きたいと感じています。
この仕事に就いて、本当に幸せだと感じています。
従業員の心身の健康増進や企業の発展・産業の成長のためにも、そして私たち自身のやりがいのためにも、現役の企業内理療師が、井の中の蛙にならず、積極的に研鑽して行くことが大切だと思います。
勿論、各職場で他の産業保険スタッフと連携して励むことがまず大切ですが、それだけではなく、外部の関係者とも連携をとって、自らの能力を高めて行くことも大切です。
企業内理療師の団体としては、≪JBHA≫という全国組織の職能団体が最も歴史が長く、組織の規模も大きく、活動が活発です。
私も幹事として関わっていますので、もし在校生の皆さんで、企業内理療師として就職されます方がいらっしゃいましたら、よろしければ、JBHAへのご入会をご検討下さい。
3 視覚障害者の自立のために
ここまでは、企業内理療師の役割と今後の課題について、私見をお話して来ました。
最後に、視覚障害者の自立のために、私たち当事者が持つべき姿勢について、ことわざや詩の紹介を通して、私見をお話させて下さい。
先ほどのお話と重なる点もありますし、また、異なる意見をお持ちの方もいらっしゃるかと思いますので、あくまでも一個人の意見としてお聴き下さい。
(1) ≪「自ら機会を創り出し、機会によって自らを変えよ」≫
私の好きな言葉をいくつかご紹介いたします。
まず一つ目が、リクルートの社訓である≪「自ら機会を創り出し、機会によって自らを変えよ」≫という言葉です。
私も含め、私たち視覚障害者は、先ほど述べました通り、≪支援されること≫に慣れ過ぎてしまっている傾向にあると思います。
成長して行くために、必要な知識や技能を身に付けるために、他力本願になることなく、自ら考え、自ら行動することが大切だと思います。
アンテナを張らなければ、情報は入手できません。
(2) 過去と他人は変えられない。自分と未来は変えられる。変えられることは変える努力をしましょう。変えられないことはそのまま受け入れましょう。おきてしまったことを嘆いているより、これからできることを考えましょう。
二つ目に好きな言葉です。
他力本願の週間が身に付いてしまうと気が付かないうちに、思う様に行かなかった時、他人や社会の性にしてしまいがちですので、自戒の意味を込めて、思う様に行かなかった時にこの言葉を思い出す様にしています。
今ある現実は、自分の言動の結果であることを意識することが大切だと思います。
(3) 「褒めい謗らいや世ぬ中野習い 沙汰ぬ無ん者ぬ 何役立つか」
ふみいすしらいやゆぬなかぬならい さたぬねんむぬぬ ぬやくだつか)
三つ目の言葉は、沖縄の言葉ですので、意味が分かり難いと思います。
「褒められるのも謗られるのも世の常。誰からも注目されない者が何の役に立つだろうか」
という意味です。
発言や行動には当然、責任が伴います。
必要以上のことを何も言わず、多少のことは見て見ぬ不利をしていれば、褒められることもない代わりに謗られることもなく、楽です。
でも、そんな人間が社会の役に立つのか?という趣旨の詩です。
試適を受けた時には勿論、真摯に受け止める必要がありますが、ただ、一生懸命頑張っているのに、自分は何もしない人から批判をされると、腹が立ってしまうものです。
そんな時にこの詩を思い出すと、私は凄く励みに感じます。
(4) 恩送り
お世話になった方に対して≪恩返し≫することは当然です。
ただ、恩返ししたくても、もうその相手が他界され、恩返しできない方もいらっしゃいます。
また、私たち視覚障害者は、お世話になった方に恩返ししたくても、物理的に難しいことも多いかと思います。
でも、お世話になった方に直接恩返しできないにしても、これから出会う方々の力になって≪恩送り≫することは、私たち視覚障害者でも可能だと思います。
眼が見えない故にできないことも沢山ありますが、見えなくてもできることも意識次第で沢山あると思います。
例えば、高齢者はIT機器に弱い方が多くいらっしゃいますが、そういった方にアドバイスをしたり、音楽を通して地域活動に参加したり、カウンセリングのボランティア活動をしたり、東洋医学の知識を活かして地域で健康教室を開いたり…。
できることは少なくありません。
私は現在、週に二回福岡市南区で、月に2回北九州にて三線の教室をボランティアで行っています。
また、カウンセリング団体に所属し、月に二回、ボランティアで相談員として活動しています。
人それぞれ興味があること・得意分野には違いがありますので、皆さんも是非、何か自分が好きなこと・得意なことを見つけ、≪恩送り≫を目指して下さい。
日頃、眼が見える方々にお世話になる機会が多い視覚障害者だからこそ、積極的にその様な姿勢を持つことが大切だと思います。
4 最後に
偉そうなことを長々とお話して来ましたが、けっして私ができている姿勢をお話した訳でなく、「こうありたい」という自分の目指している姿勢をお話させて頂きました。
理療科には、私よりご年齢が先輩の方も多く、「こんな若造が何を偉そうに言っているんだ」とお感じになった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
皆さんきっと、様々な貴重な経験・情報・人的ネットワーク等をお持ちだと思いますので、是非、ご卒業後は、本校同窓会に積極的にご参加され、私たち若者に、ご指導・ご鞭撻頂けましたら嬉しいです。
矛盾したことを言っている様に誤解されてしまうかもしれませんが、あわせてお願いしたいことは、本校卒業生の中のネットワークや、家族やヘルパーなど一部の人とだけ付き合うのではなく、是非、積極的に一般の人と関わり、皆さんのお持ちの力をご活用されて下さい。
同窓会の会長がこんなことを言うと担当の先生からお叱りを受けてしまうかもしれませんが、でも私は、同窓会に優先して参加して頂くよりも、皆さんが色々な場所でご活躍され、「○○さんは今日の同窓会に参加していないけど、どうしたんだろう」
「○○さんは今日は、◎◎という所で活躍しているよ」と、同窓生の皆さんが色々な場所でご活躍されている話題で盛り上がることの方が、とても嬉しく感じます。
決して、同窓会の行事に来なくていいと言っている訳ではございませんので、どうか誤解はされないで下さい。
今日は貴重な時間を使って、拙い私のお話をご清聴下さいまして、ありがとうございました。
